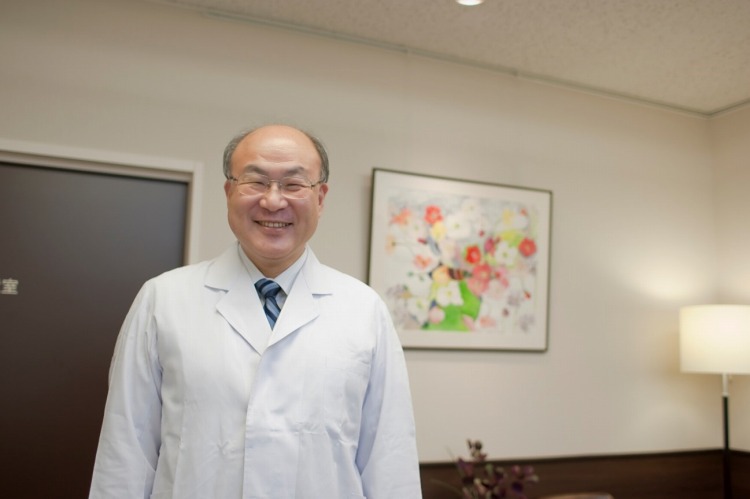委員会紹介
日本リウマチ学会(JCR)では、2018年4月より臨床研究推進小委員会を立ち上げました。この委員会のミッションは、学会員の臨床研究に関する知識と理解の向上、臨床研究を担う人材の育成を通して、日本からより質の高い臨床研究を発信することです。
本委員会は、2019年4月より臨床研究推進委員会と名を変え、JCR総会ならびに各支部会での講演活動や臨床研究トレーニング合宿を通して、若手臨床研究者の育成と良質な臨床研究の推進をサポートしています。
委員長挨拶
臨床研究推進委員会では、学会員の皆様の臨床研究に対する理解と知識の深化、ならびに次世代を担う臨床研究者の育成を通じて、日本から質の高い臨床研究を発信することを目指しています。近年のリウマチ性疾患に関するリコメンデーションや診療ガイドラインは、臨床研究によって得られたエビデンスを基盤としています。日本における診療の質をさらに高めていくためには、日本人を対象とした質の高い臨床研究の蓄積が不可欠ですが、現状ではその数が依然として限られているのが実情です。優れた臨床研究を実施するためには、研究デザインや臨床統計に関する正確かつ実践的な知識が不可欠です。JCR会員の皆様が、国際的にも高く評価される臨床研究を遂行できるよう、当委員会では以下のような取り組みを継続的に展開しています。また、我が国におけるリウマチ性疾患の疫学的実態の把握にも注力しています。
1.JCR総会・学術集会におけるシンポジウム、教育講演、Meet the Expert等の企画運営
2.臨床研究トレーニング合宿を通じた若手研究者の教育・支援
3.研究計画の立案や統計解析に関するコンサルテーション体制の整備
4.臨床研究手法に関するウェブセミナーの企画・実施
5.リウマチ性疾患に関する疫学調査の推進
今後も、臨床研究の質と実践力の向上を支援し、日本のリウマチ学研究のさらなる発展に貢献してまいります。
臨床研究推進委員会 委員長
藤尾 圭志
臨床研究推進委員会
委員長 :藤尾 圭志(東京大学医学部附属病院 アレルギー・リウマチ内科 教授)
副委員長:中山田 真吾(産業医科大学医学部 第一内科学講座 教授)
委員 :池田 啓(獨協医科大学 リウマチ・膠原病内科 主任教授)
大西 輝(京都大学医学部附属病院リウマチセンター 特定講師)
川畑 仁人(聖マリアンナ医科大学病院 リウマチ・膠原病・アレルギー内科 教授)
菊池 潤(慶應義塾大学リウマチ・膠原病内科 講師)
栗田 宜明(福島県立医科大学大学院医学研究科 臨床疫学分野 特任教授)
佐田 憲映(高知大学医学部 臨床疫学 特任教授)
庄田 宏文(東京医科大学リウマチ・膠原病内科 教授)
野間 久史(情報・システム研究機構 統計数理研究所 教授/総合研究大学院大学 先端学術院 教授)
平田 信太郎(広島大学病院 リウマチ・膠原病科 教授)
矢嶋 宣幸(昭和医科大学医学部内科学講座 リウマチ膠原病内科学部門 主任教授)
歴代委員長からのご挨拶
針谷 正祥(2023年4月~2025年4月)
臨床研究推進委員会は、学会員の臨床研究に関する知識と理解の向上、臨床研究を担う次世代の人材育成を通して、日本のリウマチ学研究者からより質の高い臨床研究を発信することを目的としています。
質の高い臨床研究を実施するためには研究方法と臨床統計学に関する正確な知識と理解が必要不可欠です。JCRの会員の皆様が、国際水準の良質な臨床研究を発信することをサポートするため、臨床研究推進委員会では以下の活動を継続的に実施しています。また、膠原病・リウマチ性疾患治療薬の開発・承認が円滑に進むように、医療機関と独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)を繋ぐ取り組みも実施しています。
1.JCR総会・学術集会、支部学術集会におけるシンポジウム、教育講演、Meet The Expertなどの企画
2.臨床研究トレーニング合宿を通しての、若手臨床研究者の育成
3.研究デザインや統計解析の方法に関するコンサルテーションシステム運営
4.臨床研究手法に関するウェブセミナーの実施
5.医療機関と独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)との人事交流の窓口
臨床研究推進委員会 委員長
針谷 正祥
西本憲弘(2019年4月~2023年4月)
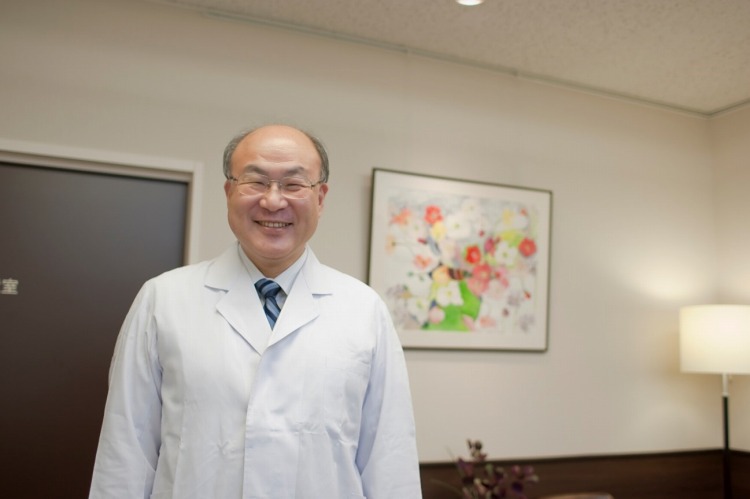
臨床研究推進委員会は、学会員の臨床研究に関する知識と理解の向上、臨床研究を担う人材の育成を通して、日本からより質の高い臨床研究を発信することを目的としています。
免疫学の基礎的研究は、複雑な免疫システムを分子レベルで明らかにしました。さらに21世紀に入り、ヒトゲノム全構造が解読され、それを利用したリウマチ性疾患の関連遺伝子の検索や病態解析が盛んに行われ、いくつかの免疫疾患では病因遺伝子も同定されています。基礎的研究は、すでに臨床応用へと移り、これまで難治性といわれてきたリウマチ性疾患の治療においても、病態形成にかかわる特定の分子の機能のみを制御する分子標的治療が今や可能になりました。この領域における日本の基礎免疫学の高い貢献度に比べ、残念ながら、日本の臨床研究は遅れていると言わざるをえません。現状では診療ガイドラインの基礎となるエビデンスは、質的にも量的にも勝る海外の臨床研究に強く依存しています。しかし、遺伝的な背景や社会的要因を含めた環境因子の違いを考えれば、日本独自の臨床研究によるエビデンスの構築は不可欠です。良質な臨床研究は、今後ますます重要になることは確実であり、JCRの会員が、国際水準の良質な臨床研究を発信していくためには、学会として積極的に臨床研究の教育に力をいれるとともに、サポート体制をつくるべきと考えています。
本委員会の主な活動は以下の通りです。
1.JCR総会・学術集会におけるシンポジウムやMeet the expertの企画
2.支部学術集会における臨床研究に関する教育講演活動
3.臨床研究トレーニング合宿を通しての、若手臨床研究者の育成
4.研究デザインや統計解析の方法に関するコンサルト事業
5.医療機関と独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)との人事交流の窓口
若手医師、研究者によるサブコミッティJapanese scientists to advance rheumatology-Clinical Research(J-STAR-CR)が、これらの教育事業の立案・実施、研究者のネットワーク作りを直接担います。
言うまでもなく、基礎研究と臨床研究は車の両輪のようなものであり、基礎研究推進委員会と協力しながら、JCRの発展に貢献したいと考えています。当委員会の活動について是非ともご注目ください。
日本リウマチ学会臨床研究推進委員会委員長
西本憲弘